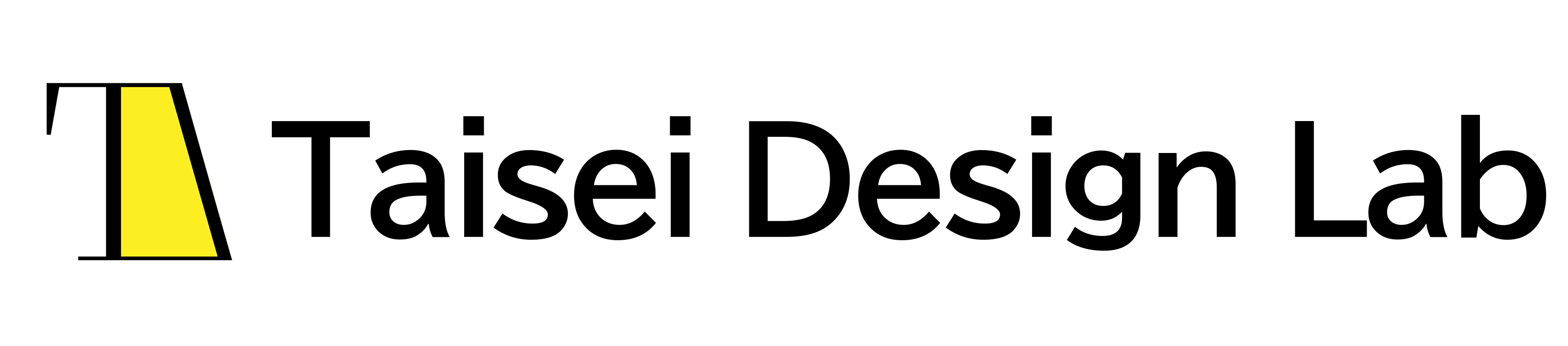欧州建築行脚44 シエナ カンポ広場/シエナ大聖堂
7月26日火曜日。
今日はシエナDAY。
カンポ広場

まるで劇場のような、傾斜を持った広場。周りは細かい石積みの建物が囲み、正面にはゴシックの市庁舎が建っている。市庁舎の前がこんな円形の傾斜地になっていると、すごく市民の広場という感じがする。伝統競馬が行われることで有名らしい。まさに市の中心ってかんじ。こういうのが市民に愛される場所なんだろうな。街の人たちが誇りに思う市政の中心、素敵だ。
シエナ大聖堂 ドゥオーモ

色彩の使われ方がフィレンツェの教会、ピサの大聖堂とよく似ている。おそらくトスカーナ地方の特徴なんだろう。緑のタイルによって作られる縞模様。ロマネスク教会、ゴシック教会と形式は変われど、模様は時代を経ても変わらないアイデンティティなのかも。

内観はこの縞模様がより一層強調されて、さらに装飾された天井、リプ、柱頭が凄まじい世界観を語っている。
この教会かつてはもっと大きく拡張させる予定だったみたい。今の主軸の身廊になってる長軸を短軸に変えて、今の短軸をさらに拡張。えげつない。その工事が途中で止まってしまった様子が見て取れた。すげーこと考える、カトリック。
言語化能力、知識、感受性

イタリアに入って、西洋建築史上の建築ばかり見ている。基本的にこれらの建築はある程度形式が決まっていて、似ているものも多い。だから特に教会なんか似たようなものばかり見ている感覚になって、現代建築のように感動する頻度が少ない気がしている。
この理由はたぶん、その建築に対して理解が足りていないから。教会建築なんて建築史で語る以上にいろんなストーリーをそれぞれもっているはず。都市的な位置付け、地域住民の生活との密着、産業との関わりなど、もっと見なきゃいけないことが山ほどあるけど、圧倒的に語るための言葉を知らないし、そこまで見ていない。実際イタリアへ入ってからブログの書くスピードが落ちている。
知識と感性はおそらく結びつく。頭でわかっているからこそ感じられるものはあるし、逆に知らなければ、そのもの自体見ようともせず素通りしてしまう。
魅力は絵画、彫刻、それ以外にも大量。そして建築を語るにはそれらの知識がないとはじまらないような感じがするくらい、教会は美術作品だと思わされる。